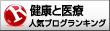貧血などの数値を見てみよう!
お薬とお付き合いのある皆さん、こんにちは!
今回も、血液検査項目の中身を深堀していきましょう!
<今回の内容>
赤血球数(RBC)

<基準範囲>
男性:430~570万/μl
女性:390~520万/μl
赤血球はご存知の方が大半だと思います。
赤血球が少なければ「貧血」ですし、逆に赤血球が多ければ「多血症」と言われます。
ちなみに「多血症」は、血液の流れが悪くなって赤血球がくっつき、血管が詰まりやすくなってしまうので要注意です。
全身状態を把握する上でも有効なため、血液一般検査の基本項目のひとつとなっています。
慢性的な倦怠感や息切れ、動悸で貧血が疑われる場合には、必ず行われます。
男女とも、300万個以下の場合は、明らかな貧血と診断されます。逆に赤血球の数が増えすぎて600~800万個になった場合は多血症といわれます。
あとは、脱水状態の時も赤血球が多くなります。
ヘモグロビン(Hb・血色素測定)

<基準範囲>
男性:13.0~16.6g/dL
女性:11.4~14.6g/dL
ヘモグロビンとは人間の血液中に含まれているたんぱく質の一種で、主に鉄を含む「ヘム」とたんぱく質でできている「グロビン」からできています。
このうち「ヘム」は酸素と結びつく力が強く、全身に酸素をいきわたらせる大切な役割を担っています。血液が赤いのもこのヘムが赤色素を持っているからです。
ヘモグロビンが低くなっている場合は、赤血球と同様「貧血」が疑われます。
逆に、ヘモグロビンが高くなっている場合は、これも赤血球同様、多血症や脱水症状などが考えられます。
それ以外にも、喫煙やストレスなどによっても数値は上昇します。
ヘマトクリット(Ht)
<基準範囲>
男性:38.5~48.9%
女性:35.5~43.9%
ヘマトクリットとは、血液中に血球の体積がどれだけの割合で存在するかを示す数値です。
血液は赤血球・白血球・血小板といった細胞成分および血しょうで構成されています。ヘマトクリットはそんな血液中の血球(細胞成分)の体積比を示す数値です。
血球の体積比としていますが、血球はそのほとんどが赤血球(約96%)であるため、実際には赤血球比として考えられています。
ヘマトクリット値が男性35.4~38.4、女性32.4~35.4の場合は「要注意」、さらに男性35.3以下、女性32.3以下の場合は「異常」となります。
ヘマトクリットが低い場合というのは血液が薄い状態、すなわち赤血球が少ないことを示しています。つまり貧血が疑われます。
逆にヘマトクリット値が男性49.0~50.9、女性44.0~47.9で「要注意」、男性51.0以上、女性48.0以上で「異常」な高値と言えます。
ヘマトクリットが高い場合は、血液が濃く、ドロドロになっていることを示しており、多血症の症状が疑われます。
脱水で見かけ上の多血になっている相対性多血症と、骨髄の異常による真性多血症があります。
前者であれば原因となる症状が解決されれば自然と元に戻りますが、後者の場合は専門医による治療が必要となります。
白血球数(WBC)
<基準範囲>
3,200~8,500/μl
白血球には大きく分けて5つの種類(好中球・好酸球・好塩基球・リンパ球・単球)があり、その役割も異なっています。それぞれが大切であり、どれか一つでも欠けてはいけません。
それぞれの働きを簡単に見てみましょう。
・好中球
白血球の大半は好中球です。血管外にいる細菌などの異物のもとに駆けつける機能と、それらを取込んで殺菌する機能を持っています。
・好酸球
好酸球は特に寄生虫の感染の際に能力を発揮します。 しかし一方で、ぜんそくやアトピーなどのアレルギー疾患の一因になりうるという側面もあります。
・好塩基球
好塩基球はアレルギー反応などに関与しているとされていますが、その存在意義や機能についての詳しい研究はあまり進んでいませんでした。しかし近年では、マダニに対する免疫を作る役割があることが明らかになりました。
・単球
単球はマクロファージともいわれ、好中球よりもやや長い時間血中に存在して、細菌だけでなく古くなった不要な細胞も食べて除去します。
・リンパ球
リンパ球は特にウイルスなどの小さな標的を攻撃する役目があります。骨髄やリンパ節、扁桃腺などのリンパ器官といわれる部位に多量に存在しています。
低い場合は2,600~3,100で「要注意」、2,500以下で「異常」、高い場合は8,600~8,900で「要注意」、9,000以上で「異常」としています。
白血球が基準値よりも多い場合は細菌感染・がん・白血病などの疑いが、逆に基準値よりも少ない場合は重症感染症や再生不良性貧血の疑いがあります。
風邪や軽い感染症などでも白血球が高くなったりもします。
白血球数の数値に異常がでた場合は、さらに詳しい血液像検査を受診することをおすすめします。
その他(MCV・MCH・MCHC)
平均赤血球容積(MCV)
赤血球の平均の容積、つまり大きさがわかります。
<基準範囲>
80~98 fℓ
平均赤血球色素量(MCH)
ヘモグロビン量÷赤血球数で算出
1個の赤血球に含まれるヘモグロビン量の平均値が得られます。
<基準範囲>
28~32 pg
平均赤血球色素濃度(MCHC)
ヘモグロビン量÷ヘマトクリットで算出
一定量の赤血球の中にどれくらいのヘモグロビンがあるかがわかります。
<基準範囲>
30~36 %
MCVが上昇しMCHCが正常
大球性正色素性貧血(悪性貧血といわれるものでビタミンB12や葉酸の不足が原因)
MCVもMCHCも正常
正球性正色素性貧血(赤血球が脊髄で作られない再生不良性貧血、赤血球が破壊される溶血性貧血など)。
MCVもMCHCも低下
小球性低色素性貧血(鉄欠乏性貧血のことで、鉄の欠乏によって起こり、貧血の大部分を占める)。